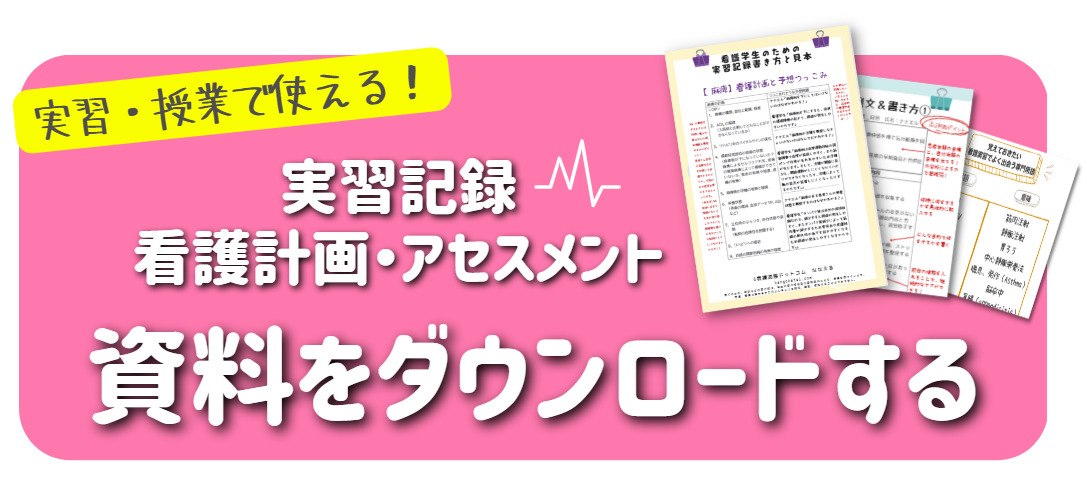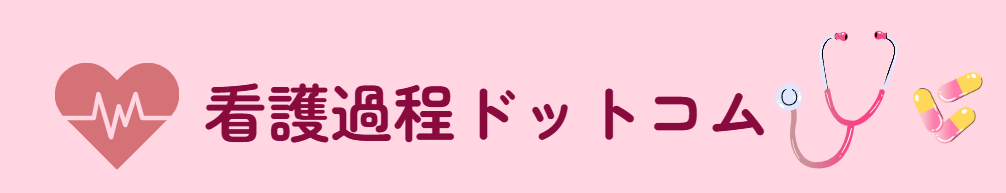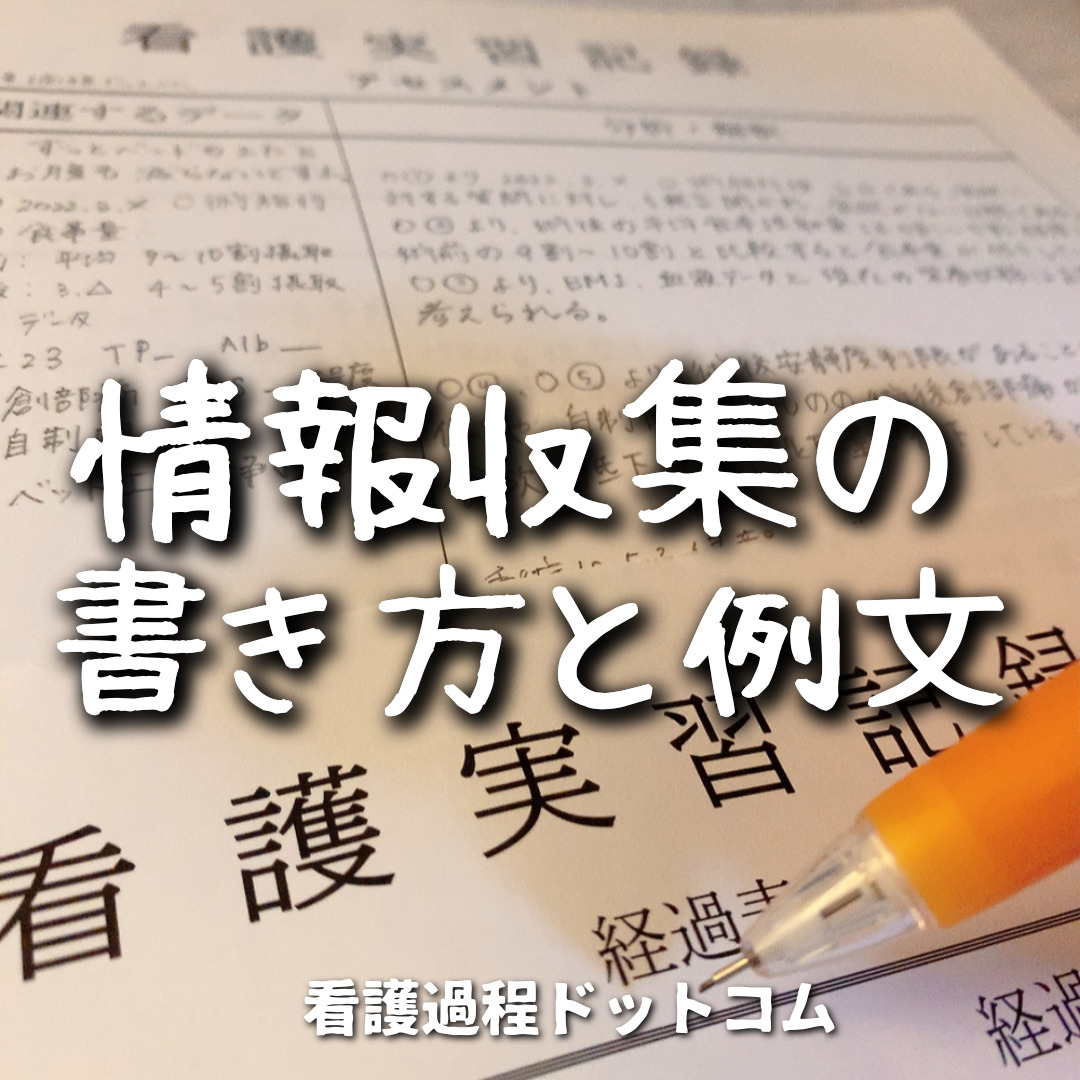情報収集とアセスメントの違い
情報収集とアセスメントは混同しがちですが、もちろんこの2つは異なるプロセスです。
「情報収集」であつめた情報をもとに、「アセスメント」で分析をします。
そのため、アセスメントに出てくる情報は、すべて「情報収集」の項目に書いてある事柄であるはずで、アセスメントで突然出てくる情報はあってはならないのです。

アセスメントを読み返してみて、
(1)書いている情報がすべて「情報収集」に書いてある内容か?
(2)「情報収集」に書いてあるのに使っていない情報はないか?
の2点を確認するのがオススメですよ~!
S情報(主観的情報)の書き方
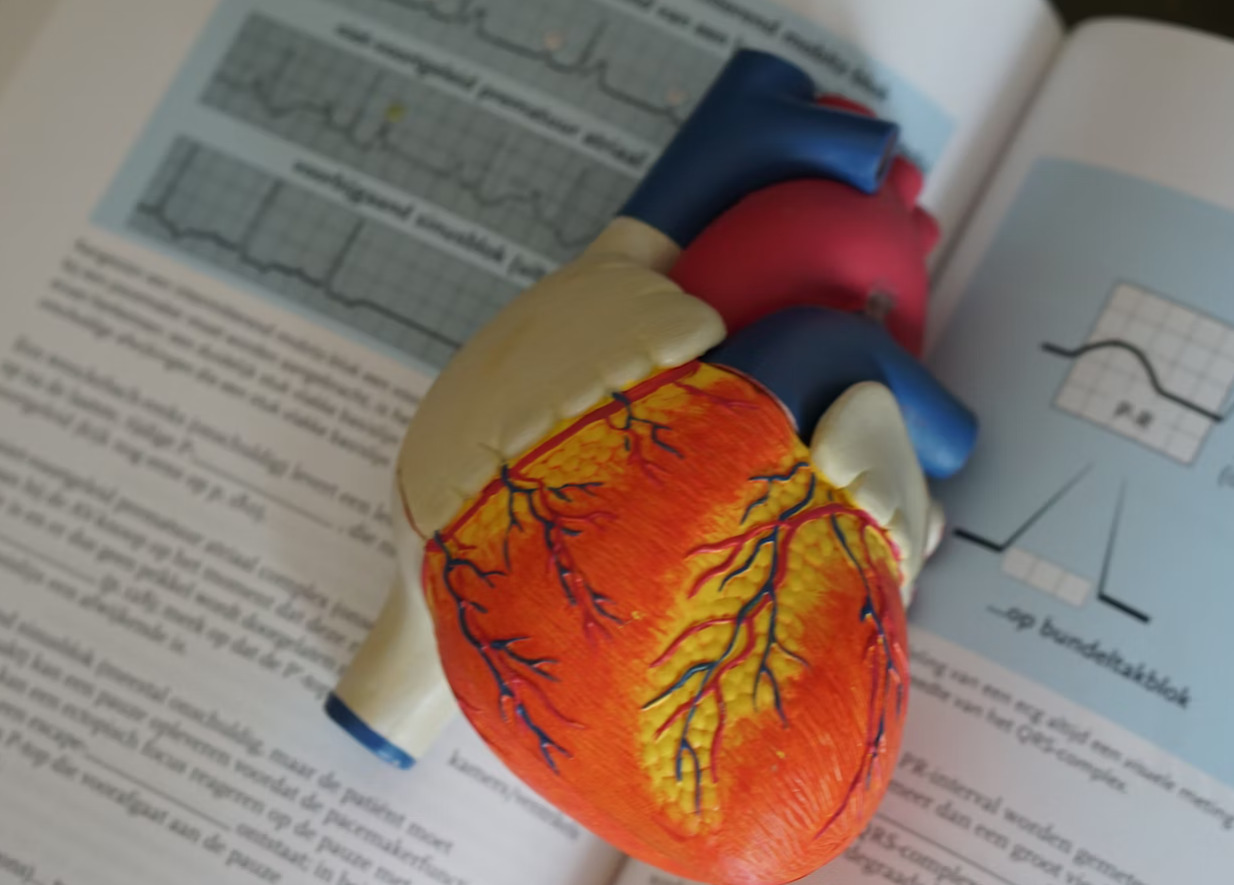
患者さんの言葉をそのまま、あるいは要点が伝わるようにまとめて書くのがコツ。
看護学生が間違えやすいポイント
【睡眠・休息】
× S:よく眠れたよ。あと、今日のリハビリは時間変更できないかな。と語る。
〇 S:よく眠れたよ
会話に出た内容でも、アセスメントに使わない情報は書かない。
「~と語る」という言葉は必要ない。
O情報(客観的情報)の書き方

主観的情報(S)や、看護者の憶測が混じりやすいのでしっかり区別して書くのがコツ!
看護学生が間違えやすいポイント
【睡眠・休息】
× O:身体を動かす時に、創部が痛そう。
〇 O:創部の疼痛の程度はNRS5~6。体動時に顔をゆがめる。
「~そう」という看護者の憶測は「O情報(客観的情報)」には書かない!
疼痛や食欲、満足度など患者の主観的な情報はなるべく数値化するとわかりやすい!
情報収集の2つの方法

看護過程における情報収集は、看護理論を用いた方法と、全体像を把握するための書式を用いる方法があります。
看護理論を用いた方法では、よくヘンダーソン、オレム、ロイが使われます。学校によっては複数の看護理論を組み合わせてオリジナルの枠組みを作ることもあります。
| 看護理論 | どのようにアセスメントするか |
|---|---|
| ヘンダーソン | 14の基本的欲求が充足しているか、常在条件、病理的状態がどう影響しているかを解釈する |
| オレム | 普遍的セルフケア要件、発達的セルフケア要件、健康逸脱に対するセルフケア要件に分かれている。自力でセルフケア要件を充足できるかを解釈する |
| ロイ | 生理的機能、自己概念、役割機能、相互依存の適応様式について、適応行動か解釈する |
全体像を把握する書式には、NANDA-Iやゴードンの機能的健康パターンがあります。
情報はどこから集めればいいのか

- 患者の発言から収集する
- 患者を観察して収集する
- バイタル結果や検査結果から収集する
- カルテから収集する
- 患者を取り巻く多職種や、家族から収集する
一口に「情報収集」といっても、これだけの情報源があります。
看護過程を展開するために、受け持ってから1~2日を目安でこれらの情報源から効率よく、必要な情報を集める必要があるわけです。
項目はすべてすぐに埋めなくてもいい
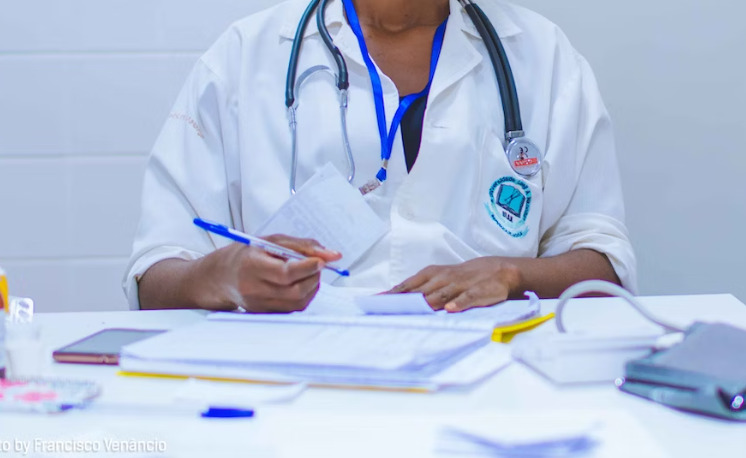
情報収集は、患者に必要な看護を実践するために行うため、必要がなければ後回しにしても問題ありません。
とくに「宗教に関する情報」や「性に関する情報」は、看護学生が悩むことが多い項目です。
患者さんにいまどんな看護が必要か?そのためにはどんな情報が必要か?を考えて必要がなければ、実習開始1、2日ですぐに埋める必要はありません。
コミュニケーションをとりながら情報収集する方法

うまく必要な情報がとれるかが不安です…

情報収集することに集中しすぎて質問攻めにならないように注意しましょう!
質問攻めにならないように、必要な情報収集をするためには、適切なタイミングや状況を見極めて、患者さんが話しやすい環境を整えることが大切です。信頼関係を築きながら情報を得ることで、適切なケアを提供することができます。

気づいたら質問ばかりしちゃいそう…。

何気ない会話をしながら質問を織り交ぜていく感じで進めてみよう。
例えば、『飲食』の項目では、患者さんとのコミュニケーションを通じて食事に対する興味関心や食欲の有無を観察することが重要です。
「もうすぐお昼ですね〜今日はどんなメニューですかね☺️」
と軽い会話を交えながら、患者の食事への興味、関心を観察!
「私はおなか空いてきました〜。○○さんは空き具合はいかがですか?」
と質問しながら、患者の食欲の有無を確認します!!
もし食欲がない場合は、なぜ食欲がないのかをアセスメントします。疾患の症状なのか、不安など精神的な問題が関係しているのか、薬の副作用が影響しているのかなど、様々な要因を考慮します。
質問攻めではなく、コミュニケーションを通じて情報を収集することが大切です。
↑書籍では、情報収集の仕方・コミュニケーションの取り方などもくわしく解説していますので、ぜひご覧になってみてくださいね。
【ストレス耐性】の情報を収集したい場合はこんなコミュニケーションをとることができます。
- 看護師: 最近、お仕事や入院生活でストレスを感じることはありますか?
- 患者: うーん、特に大きなストレスは感じていませんが、たまに退屈でイライラすることはありますね。
- 看護師: そうなのですね。そんな時はどのように対処されていますか?
- 患者: 基本的には読書や音楽を楽しんだり、散歩に出かけることで気分転換を図っています。
【家族の協力関係】を観察したい場合はこんなコミュニケーションをとることができます。
- 看護師: ご家族の方は、〇〇さんの入院生活をどのようにサポートされていますか?
- 患者: 家族は私のことをとても気にかけてくれています。毎週末にはお見舞いに来てくれたり、手紙や電話で励ましてくれたりします。
- 看護師: それは素晴らしいですね。家族の方とのコミュニケーションは頻繁に取れていますか?
- 患者: はい、日常的に連絡を取り合っていますし、悩みや不安なども相談できる環境です。
患者さんと話している時は、患者さんの言葉だけでなく患者さんの表情・しぐさ・声のトーン ため息 視線などはすべて重要な情報です。言語によるコミュニケーションだけでなく、非言語コミュニケーションも大切にしましょう。

患者さんの前では、メモもできるだけ控えるようにしましょう。
最後は、患者さんに話をしていただけたことに感謝の気持ちを必ずお伝えしましょう。 たとえば、
「〇〇さん、いろいろなお話を聞かせていただき、ありがとうございました」
と、笑顔で真心のこもったあいさつを心がけてくださいね。
患者さんに負担をかけない情報収集
情報収集するときは、まず患者さんの一日のスケジュールを把握して、なるべく負担が少ない時間帯にコミュニケーションを組み込みましょう。
(リハビリ直後は避ける、など。)
また、お話させていただくことについて本人の承諾を得ましょう。たとえば
「〇〇さん、こんにちは。今よろしければ、10 分ほどお話をさせていただきたいのですが、いかがでしょうか?」
と、時間の目安を示して意向を確認するのがおすすめです。
会話中も、患者の表情や声のトーンに注意して疲労感がないか観察し、「お疲れではありませんか?」といった声かけも大切です。
ゴードンの機能的健康パターンとは

マジョリー・ゴードン(Marjory Gordon)博士が考案した11の機能面からみた「健康パターン(Functional health pattern)」は、1970年代に発表された膨大な数のアセスメントフォームの見直しと分析によって、アセスメントのための共通領域が浮かびあがり、考案されました!
この枠組みは、看護理論で共通する概念である人間と環境の相互作用を全人的にとらえたうえで、機能的に分類しているのであらゆる看護理論で使うことができます。
ゴードンの情報収集のテンプレート
| パターン | どんな情報をあつめるのか? | 質問の仕方(セリフ例) 自然な会話の流れに組み込み、 患者から情報を収集しましょう |
|---|---|---|
| 健康知覚ー健康管理 | ・自分の健康状態をどのように知覚しているか (現病歴、既往歴、治療方針、疾患や治療への理解) ・健康管理状況に問題はないか (受診行動、自己管理の遵守と程度、健康増進のための活動はできているか) | 「自分の健康状態について、どのように感じていますか?」 「自身の健康に関して、何か心配や不安があることはありますか?」 →直接的すぎる場合もあります |
| 栄養ー代謝 | ・食習慣に問題はないか (入院前後の食事内容、回数、時間、量、嗜好) ・栄養状態に問題ないか (BMI、血液データ:TP、Alb、RBC、Hbなど) ・皮膚状態と治癒力 (皮膚や粘膜の状態、褥瘡の有無) | 「このメニュー、美味しそうですね。お食事は十分にお召し上がりいただけそうですか?」 |
| 排泄 | ・排泄習慣に問題ないか (排便パターン、排泄方法、量、腸蠕動音) ・下剤使用の有無 ・ドレナージからの排液量や性状 | 「入院前は、お手洗いに行かれる頻度はいかがでしたか?」 →入院中は記録や、実際に患者を観察して把握するとよい◎ |
| 活動ー運動 | ・身体活動状況に問題ないか (ADL、運動機能、種類、日常生活活動、移動方法) ・余暇活動に問題ないか | 「お散歩や身体を動かすことはお好きですか?」 |
| 睡眠ー休息 | ・睡眠習慣に問題ないか (睡眠時間、規則性、満足度、日中の過ごし方) ・眠剤の使用 | 「朝起きたときにスッキリとした感じはありますか?」→熟眠感の観察! |
| 認知ー知覚 | ・感覚の障害の有無と程度 (視覚、聴覚、味覚、嗅覚、触覚) ・痛みの知覚と対処方法 ・認知に影響を及ぼす障害 (意識レベル、見当識、言語、記憶、判断などの能力) | 「痛みの強さに変化はありますか?」→どんな時に痛むのか?強さはどうか?「「痛みの強さを0から10で表現するとしたら、今の状態はどのくらいですか?」」 |
| 自己知覚ー自己概念 | ・アイデンティティ、ボディイメージに問題ないか (自己に対する認知、態度) ・イメージ、価値観、今後の疾患の見通し | 「自分のアイデンティティや人としての意味を考えることはありますか?」 →直接的すぎる場合もあります |
| 役割ー関係 | ・家事や仕事、地域での役割と関係に問題ないか (家族関係、キーパーソン、家族の健康状態、家庭内・社会での役割、職業や経済状況) | 「ご家族や仕事、学校などで果たす役割について、どのように感じていますか?」 →と聞くのは直接的すぎる場合もあるので 「日常生活の中で、家族や友人たちとの役割分担はありますか?」 と質問し、 「ご家庭では__をされていたのですね」 と役割を復唱し、患者の反応や受け止めを観察するなど |
| セクシュアリティー生殖 | ・セクシュアリティや性的関係についての満足度 (性的アイデンティティ、適切な性的関係) ・生殖機能に問題はないか (月経の状況、妊娠状況) | O情報があれば、O情報をもとに 「_について、何か気になることはありますか?」 |
| コーピングーストレス耐性 | ・ストレス耐性 (ストレス対処法や、その頻度) ・家族の協力関係 (サポート体制、家族の患者に対する認識) | 「入院中に、特に気になることや困っていることはありますか?」 |
| 価値ー信念 | ・健康に関連した価値、信念、葛藤 (患者が何を正しいと考えるか、意思決定のベースとなる価値観) ・人生で重要だと感じられる事柄 | 「病気や入院生活において、どのようなことが心の支えになっていますか?」 |

これらの質問は、自然なコミュニケーションの一環としてさりげなく情報を収集しましょう。
相手に圧迫感を与えず、穏やかなトーンで話題を提供し、患者さんが自身の健康状態や管理について思いを語りやすい環境を作りましょう。
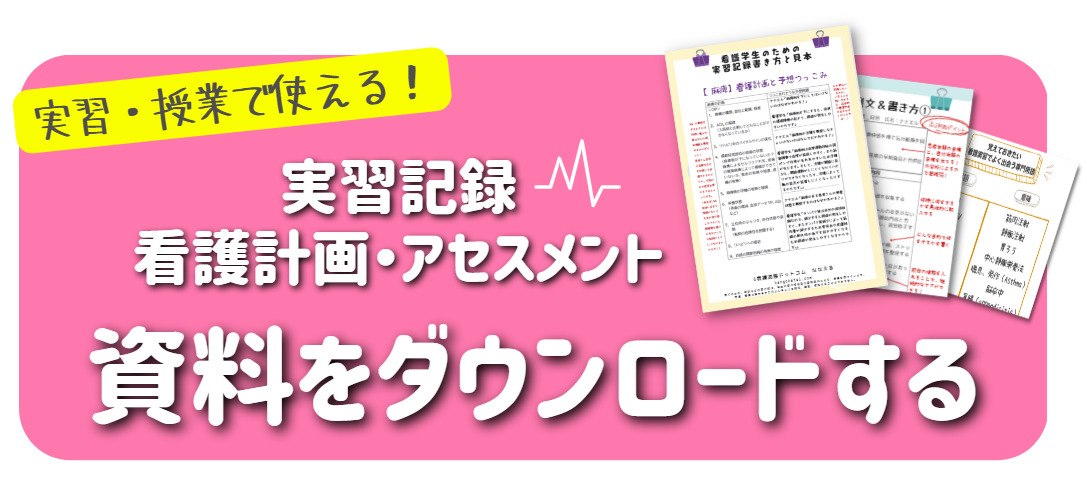
ヘンダーソンの基本的欲求と基本的看護の構成要素

ヴァージニア・ヘンダーソン(Virginia Henderson)は、看護を必要とする人は「体力、意思力、知識」のいずれかが不足しているため、その人の足りない部分を担うことが看護の機能であることを表現しました。
看護計画を必要とする人の基本的ニードとして14の要素を挙げ、これらの基本的ニードに対応するように患者の行動を援助するのが基本的看護としました。
また、看護を必要とする人の基本的ニード(欲求)に影響を与えるものとして、常在条件と病理的状態があると述べています。
常在条件ってなに?

- 年齢
- 性別
- 性格
- 家族構成、キーパーソン、関係性
病理的状態ってなに?

- 診断名
- 現病歴
- 症状、検査データの所見
- 治療方針(食事・運動・手術・内服)
- 患者への説明内容
ヘンダーソンの情報収集テンプレート

| 基本的欲求 | どんな情報をあつめるのか? | 質問の仕方 (自然な会話の流れに組み込み、 患者から情報を収集しましょう) |
|---|---|---|
| 呼吸 | 安楽に呼吸できるか、ガス交換が正常か (呼吸数、呼吸困難の有無、呼吸パターン、血液ガス) | 「息苦しさはないですか?」 →唐突すぎるので、労作時などに。 |
| 飲食 | 必要な栄養が摂れているか、食事の満足感があるか (栄養状態、血液検査(TP、Alb、Hb、TGなど)、食事摂取状況、水分摂取、嚥下機能) | 「美味しい匂いが漂ってきますね。おなかの空き具合はいかがですか?」 |
| 排泄 | 正常な排泄ができているか、排泄物に異常はないか (排泄パターン、回数、性状、量、方法、血液データ(BUN、Cre、GFRなど)、in-outバランス、ドレーン等の排液) | 「お身体の調子によって、排尿や排便の回数は変動することもあるかと思いますが、最近はいつもと変わりありますか?」 →タイミングや質問する場所を考えてすること |
| 姿勢・活動 | 身体を動かし、よい姿勢を保持できるか (ADL、手足の可動性・障害の有無、歩行、姿勢、1日の過ごし方) | 「お散歩や軽いストレッチなど、身体を動かすことは好きですか?」 |
| 睡眠・休息 | 睡眠と休息をとれるか (睡眠時間、睡眠パターン、眠剤の有無、ストレス状況) | 「お気に入りの寝具や寝る前の習慣などはありますか?」 |
| 衣服 | 適切な衣服を選び、着脱できるか (身だしなみ、嗜好、暑さや寒さへの対処、着脱行為の自立) | 「この色、素敵ですね。気分に合わせて色や衣類を選ぶことって、心地よさを感じますよね。」 →場面によるが、さりげない会話の中から引き出せるとよい |
| 体温・循環 | 衣服の調節と環境の調節で体温を生理的範囲内に維持できるか (体温、脈拍、血圧、体温に変化を与える環境はないか、脱水の有無) | 「この時期、気温の変化が激しいですよね。○○さんは、暑さや寒さには敏感ですか?」 |
| 清潔 | 身体を清潔に保ち、身だしなみよく、皮膚の保護ができているか (清潔の程度、清潔行動の種類と頻度、皮膚の状態) | 「お顔をふくだけでもさっぱりしてリフレッシュされますよね?」 →清潔への興味関心の程度、現在の清潔の頻度に満足しているか?など |
| 安全 | 環境の危険を避けて、また他者を傷害していないか (自分で環境調整できるか、感染予防のリスク、療養環境の危険な箇所とその理解) | 「お部屋の中で歩きづらい、ものが取りづらい部分などはありませんか?安全に過ごせるように心配りしていますので、どんなことでもお気軽にお伝えくださいね。」 |
| コミュニケーション | 情動や欲求、恐怖や意見を表現し、意思伝達できているか (コミュニケーション機能障害の有無、家族や友人との関係、悩みの表出) | 「面会ではご家族と十分お話できましたか?」 →面会のあとなどに。 「コミュニケーション面で何か要望や気になることはありますか?」 |
| 宗教 | 自分の信仰や、自分の善悪の考えに従って行動できているか (患者が大切にしている考え方、宗教による入院生活への抑制) | 「◎◎さんの大事にしている信念や習慣に関して、もし私たちがお手伝いできることや配慮することがあれば、お教えいただけるとうれしいです。」 →質問する場合は、タイミングや場所に気を付けること |
| 生産的な活動 | 何かをやり遂げた感覚をもたらす活動をできているか (職業、社会的役割、入院や疾患による仕事や役割への影響、経済状況) | 「お仕事や日常生活で達成感を感じるようなことはありましたか?」 |
| レクリエーション | レクリエーション活動をできているか (趣味、入院前後の余暇時間の過ごし方、入院中の気分転換方法) | 「最近、楽しまれることや気分転換をされる機会はありますか?お好きな趣味やレクリエーションのアクティビティがあれば、ぜひ教えてください。 |
| 学習 | 学習や発見をし、好奇心が満たされているか (認知機能、学習意欲) | 「面白そうな本をお持ちですね。いつから読まれているんですか?」 「◎◎さんが興味があるのはどのような分野ですか?」 |
ロイの適応看護モデルとは

シスター・カリスタ・ロイ(Sister Callista Roy)の看護モデルは、対象者がおかれた環境に適応しようとする状況を肯定的な対処としてとらえる概念をベースとした「適応看護モデル」です。
ロイの適応看護モデルの構成要素は(1)看護ケアを受ける「人間」(2)看護の具体的「適応の目標」(3)「健康」の定義(4)「環境」についての意味(5)「看護」活動の領域の明示の5つであり、
人間は多くの部分からなり、相互に関係しあってできた1つのものである、という考え方をします。
そして「生理的様式」、「自己概念様式」、「役割機能様式」、「相互依存様式」の4つの機能様式から、患者の適応状況をみます。
つまり・・・
ロイは「人は変化する環境に適応するための対処機構をもって反応し、その人の目標を維持しようとする」と考えます。そしてその適応の手段を4つの適応様式に分類し、これら4つの様式の状態について適応反応か非効果的反応かどうか、適応状況を判断する。そしてその人の適応を促進することを支え、健康に導くことが、ロイの適応看護モデルの看護の目標となるわけです。

4つの視点から患者さんを理解するってことか!
| 機能様式 | どんな情報をあつめるのか? |
|---|---|
| 生理的様式 (身体面では どのように反応 しているのか ?) | 人間が環境からの刺激に対して身体面でどのように反応しているか?? 【基本的ニード】 (1)酸素:呼吸数、リズム・深さ、呼吸音、SpO₂、脈拍数、リズム、心拍数・心音、心電図、血圧 (2)栄養:栄養状態、食事内容、回数、量、水分摂取量 (3)排泄:回数、量、方法、検査データ(尿pH、BUN、Cr、eGFR、尿比重)、腸蠕動音 、下剤の使用 (4)活動と休息:運動と休息の割合、入院前後の活動パターン、MMT (5)保護:保清行動、皮膚や毛髪などの状態、掻痒感の有無、発汗の有無 【プロセス】 (6)感覚:視覚、聴覚、味覚、嗅覚、皮膚感覚、疼痛 (7)体液と電解質:体液と電解質バランス、浮腫、電解質異常(Na、K、Cl、Ca、Mgなど) (8)神経学的機能:意識レベル、見当識レベル、認知機能、運動反応 (9)内分泌機能:内分泌機能や代謝、ストレス反応 |
| 自己概念様式 (自分自身の 考え方や感情 、行動を導く もの) | 対象者が自分自身に対する考え方や行動 (1)身体的自己:身体感覚、健康や疾病の状況とその認識 (2)個人的自己:自分の特性や可能性、価値に対する自己評価 |
| 役割機能様式 (社会において もつ役割) | 人間が社会のなかで占める役割 (1)一次的役割:年齢、性別、発達段階 (2)二次的役割:一次的役割に伴う課題(家庭内の役割) (3)三次的役割:自由に選べる一時的な役割(社会的役割、ボランティア、趣味) |
| 相互依存様式 (人との密接な 人間関係) | 人間関係、サポート状況、経済状況 |